- HOME
- アンチエイジング情報
- オリゴ糖とは
アンチエイジング情報TIPS
アンチエイジング情報TIPS
2016.10.17
オリゴ糖の多くはブドウ糖よりもカロリーの低い甘味料であり、さらに腸内環境を整えると言われ注目を浴びています。今回は、オリゴ糖とはどんな食品成分なのか、またどのような働きがあるのかについてご紹介します。
オリゴ糖(oligosaccharide)はブドウ糖などの「単糖」が数個繋がったものの総称です。一般的にはおおよそ3糖〜10糖のものをオリゴ糖と呼びます。
ちなみに、難消化性オリゴ糖と同じく、う触性が低いとして知られるキシリトールやマルチトールなどの「糖アルコール」は単糖や二糖類が一部変化した化合物です。
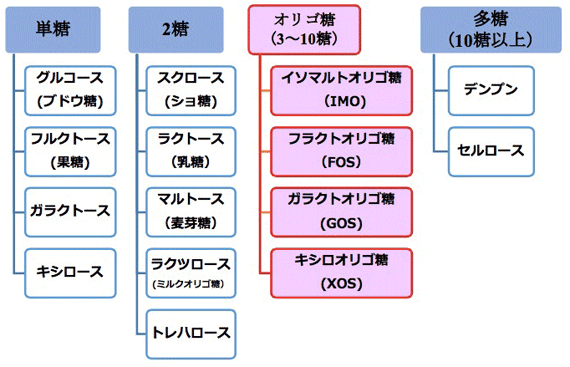
それぞれのオリゴ糖は、構成する単糖や2糖の種類が異なります。また、ヒトの消化酵素で消化できる糖(可消化性)と、できない糖(難消化性)が存在し、一部の難消化性オリゴ糖は腸内細菌によって利用されます。
主なオリゴ糖 |
主な構成 |
結合 |
| イソマルトオリゴ糖 (一部難消化) Isomalto-Oligosaccharide |
 |
α1-6 |
| フラクトオリゴ糖 Fructo-Oligosaccharide |
 |
β1-2 |
| ガラクトオリゴ糖 Galacto-Oligosaccharide |
 |
β1-4 |
| キシロオリゴ糖 Xylo-Oligosaccharide |
 |
β1-4 |
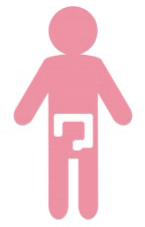 全ての腸内細菌が全てのオリゴ糖を利用できるというわけではありません。もともとオリゴ糖が「ビフィズス菌増殖因子」として発見されたように、基本的にビフィズス菌は他の菌種に比べ多種類のオリゴ糖を利用することができます(多様な糖トランスポーターを有する)。先の4つのオリゴ糖は小腸では消化されず、大腸においてビフィズス菌のエサになりやすいとされています。しかし、中にはイソマルトオリゴ糖は利用できるがフラクトオリゴ糖は利用しにくいなどという菌も存在します。
全ての腸内細菌が全てのオリゴ糖を利用できるというわけではありません。もともとオリゴ糖が「ビフィズス菌増殖因子」として発見されたように、基本的にビフィズス菌は他の菌種に比べ多種類のオリゴ糖を利用することができます(多様な糖トランスポーターを有する)。先の4つのオリゴ糖は小腸では消化されず、大腸においてビフィズス菌のエサになりやすいとされています。しかし、中にはイソマルトオリゴ糖は利用できるがフラクトオリゴ糖は利用しにくいなどという菌も存在します。
一般的にオリゴ糖の生理作用として知られるのは、腸内細菌がオリゴ糖を利用(資化)した際に産生する酢酸、酪酸といった短鎖脂肪酸などによるものです。また増殖した菌体自身にも生理作用があると考えられています。
主な短鎖脂肪酸 |
生理的作用 |
| 酢 酸 Acetic acid |
◆大腸上皮細胞のバリア機能向上 ◆変異細胞(がん細胞)の細胞死誘導 ◆肝臓で脂肪合成・コレステロールの前駆体 ◆末梢組織でエネルギー源(ケトン体) |
| 酪 酸 Butyric acid |
◆大腸上皮細胞の機能維持(主なエネルギー源) ◆大腸炎・アレルギーの抑制(Treg分化への誘導) ◆変異細胞(がん細胞)の細胞死誘導 |
また、短鎖脂肪酸等によって大腸内のpHが下がるため カルシウムやマグネシウムなどが吸収されやすくなるとも 考えられていますが、詳細な機序は不明です。
オリゴ糖は生理的機能性に着目されていますが、加工食品への品質向上目的でもよく利用されます。
例えば、イソマルトオリゴ糖はもともと清酒、みりん、味噌などに含まれる成分(麹菌により産生)で、耐熱・耐酸性に優れ、まろやかで旨味のある甘み、煮崩れ低減効果を有するとして冷凍食品などに使われています。
また、天然食物にもオリゴ糖が含まれ、フラクトオリゴ糖はアスパラガス、にんにく、ゴボウ、玉ねぎ、蜂蜜などに多く含まれていることが知られています。
【参考】独立行政法人 農畜産業振興機構サイト「お砂糖豆知識[2004.10]、食品機能性の科学(株産業技術サービスセンター)、Milk Science Vol.64,No.2 2015、化学と生物Vol.52,No.9,2014、ルミナコイド研究のフロンティア(建帛社)、昭和産業㈱サイト「イソマルトオリゴ糖について」、ヤクルト中央研究所サイト「健康用語の基礎知識」、国立健康・栄養研究所サイト
2016.06ヘルシーパス提供